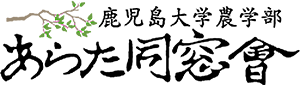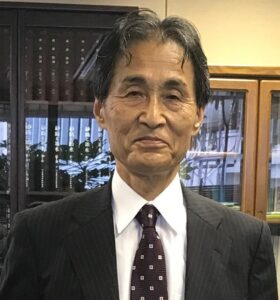
あらた同窓会会長
下川 悦郎
あらた同窓会会員の皆様におかれましては、ますますご健勝でお過ごしのこととお慶び申し上げます。日頃は同窓会の運営にご支援ご協力いただいていることについて厚く御礼申し上げます。
このたび令和6年度総会の議を経て会長に就任いたしました下川悦郎と申します。昭和44年度林学科の卒業です。会長の重責を担う器ではないと自覚しておりますが、お引き受けした以上その職責を果たしていく所存です。前任の藤田晋輔会長同様、同窓会運営にたいする会員各位のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。
令和5年5月新型コロナ禍が解除されたことで、昨年度(令和5年度)からあらた同窓会は新型コロナ禍前の活動を少しずつ取り戻しつつあります。学生向け講演会は準備不足で開催に至りませんでしたが、令和5年度卒業(学部学生)・修了(大学院修士課程)祝賀会(3月25日 農学部との共催)や令和6年度新入生茶話会(4月3日 主催)、総会終了後の懇親会、各支部との交流会など、恒例の行事が農学部との連携で開催されました。コロナ禍でも発行されていた会報は引き続き発行されています。それから初めての開催となりましたが、11月23日令和6年度同窓会総会に先立ってホームカミングデーと称して在校学生の綱引き大会などの行事が行われました(農学部主催、同窓会共催)。この催しは今後も毎年開催されるとのことですので、あらた同窓会総会・懇親会に出席かたがた母校を訪問していただければと思います。
同窓会活動については、改善しなければならない課題があります。二つ挙げておきます。一つは会費の納入者数が低い状態で推移していることです。令和5年度の一般正会員の納入者数は828人、物故者を除く会員数は推定1万5千人を数えますので、納入率は5.5パーセントです。結果、同窓会の財政基盤は脆弱で、会費収入だけでは予算が組めない状況が続いています。経費節減はもとよりですが、会費免除者や旧賛助会員の方々からのご寄付(賛助金)をいただき、また新型コロナ禍での同窓会活動の中止や縮小に伴って生じた繰越金を充てることで辛うじて単年度の収支バランスが取れているのです。
会計年度末、本部では同窓会総会が、各支部では同窓会支部総会が開催されています。年に一度会員が集う恒例の行事ですが、本部、支部とも出席者数が減少していると感じています。世代を超えて会員が集い交流と親睦を図るという同窓会の原点ともいえる活動が弱くなっているのではないか、これが二つ目の課題です。こうした課題を少しでも改善するために努力したいと思っています。
母校の農学部では、農学分野における教育研究機能の強化と時代をリードする人材の育成を図るために、「鹿児島大学農学部基金」が設立され、寄付を募っています。あらた同窓会会則第2条にあるように、農学部の発展に寄与することも同窓会の目的です。会員の皆様におかれましては基金の趣旨をご理解いただきご支援をお願いする次第です。
簡単ですが会長就任のご挨拶とさせていただきます。

農学部長(あらた同窓会顧問)
山本 雅史
あらた同窓会の会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より、同窓生の皆様から農学部学生および教職員へのご支援を頂いておりますこと、厚くお礼申し上げます。
さて、鹿児島大学農学部は令和6(2024)年度に大幅な教育組織改革を実行し、従来の3学科制を1学科4教育プログラム(PG)(植物資源科学PG・環境共生科学PG・食品生命科学PG・農食産業・地域マネジメントPG)制としました。これは、学生がそれぞれのキャリアプランに基づいて履修すること、現場重視の教育と高度な学問的知見・技術との融合を図ることを目的としています。これらによって、農林食産業全体を理解する農業総合力と専門性を兼備するだけでなく、既成概念に捉われない思考による新たな価値の創造やビジョンの形成、先進的視点と新技術を駆使して課題解決ができる人材の育成を図ることができると考えています。
また、研究面では、特に現在世界が求めている持続的な社会の構築を目指し、食料生産力向上、食と安全、生物多様性、環境問題に取り組まなければなりません。気候変動(地球温暖化)に起因する問題解決に関する研究も必要です。特に鹿児島の地域性を活かした分野、鹿児島でしかできない研究の推進が重要です。世界自然遺産の屋久島や奄美などの島嶼域、地熱や温泉などの自然エネルギー、ユネスコの無形文化遺産に登録された「伝統的酒造り」である焼酎など、世界の中で鹿児島にしかないものが多数存在します。いずれも農業・環境・食品に大きく関わるものであり、農学部ではこれらの特徴を積極的に活かした教育研究を進めることによって地域だけでなく世界にもその成果を還元することを目指します。
今後の農学部の発展には、社会との緊密な連携が必要です。そのためには同窓会の皆様のご協力が不可欠です。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。また、末尾になりますが、同窓生の皆様のますますのご健勝とご多幸を、ならびにあらた同窓会のご発展を心より祈念申し上げます。