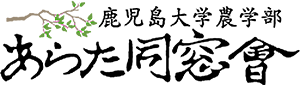あらた同窓会会長
藤田 晋輔
わが母校の始祖、鹿児島高等農林学校は南方開発の使命を抱え、国立の高等教育機関として、1909年(明治42年)「あらた」の地に開学、第1回の入学宣誓式が挙行され、114年の歴史を刻みました。この間、1944年(昭和19年)鹿児島農林専門学校と改称し、1949年(昭和24年)の学制改革に伴い鹿児島大学農学部に引継がれました。爾来20,000名を越える卒業生を輩出しています。多くの先輩諸氏は国内外の行政、研究、そして実業・産業界で高い目標と使命感を持ち活躍されています。
このような歴史を有する母校の「あらた同窓会」会長の重責を、はからずも担うことになり、身の引き締まる思いを致しております。私は1962年(昭和37年)林学科を卒業、同年京都大学大学院に入学、修了後、1964年島根大学、1969年静岡大学、そして1980年から鹿児島大学(農学部)に奉職しました。爾来2004年3月定年まで鹿児島大学の24年間お世話になりました。学生時代を含め、文部省(現在文部科学省)、建設省(現在の国土交通省)、農林水産省(林野庁)、国有林現場、そして、鹿児島大学卒業生が多い静岡県庁、鹿児島県庁を始めとする県内外各自治体、産業界等の多くの同窓生各位に大変お世話になりました。改めて心から謝意を表します。ところで、鹿児島県出身の初代校長玉利喜造先生は、明治42年国策により「あらたの地」に創設、開学されたわが母校の整備充実と開学の思想に基づく挑戦すべき課題に情熱と心血を注がれました。中でも、当時の国策でもあった南方開発を見据えた地域の農林業を基軸とした地球規模の食糧事情や環境改善等の解明、展開のため果敢に挑戦する地として最適の場であったと考えています。明治期の創設、開学以来海外への展開を使命とした実践教育を受けた有能な卒業生諸氏は、開学の精神のもと各々の職域で枢要な職域、地位で実績を残されてきました。
このような実践的歴史を引き継いだ現鹿児島大学農学部においても、近年では、創設期と類似した体験的な実験実習等が東南アジア諸国のフールドにおける教育も重視し、豊かな人間性、現場における実践力、優れた応用力、広い視野と国際性に通じる涵養の教育が行われています。明治の創設期とは、国際的な時代背景が異なりますが、これまでのJAICA等を通した諸先輩方の輝かしい実績と伝統を引き継ぐためにも、今後も先人的思想で、且つ実践的志向を所持した卒業生の輩出を期待しています。
これからも同窓会役員各位の御助力を戴きながら、運営に従事して参りたいと存じます。
あらた同窓会会員各位におかれましても、「農学部あらた同窓会」および「鹿児島大学農学部」の発展のために、今後ともご指導、ご支援賜りますようお願い申し上げます。
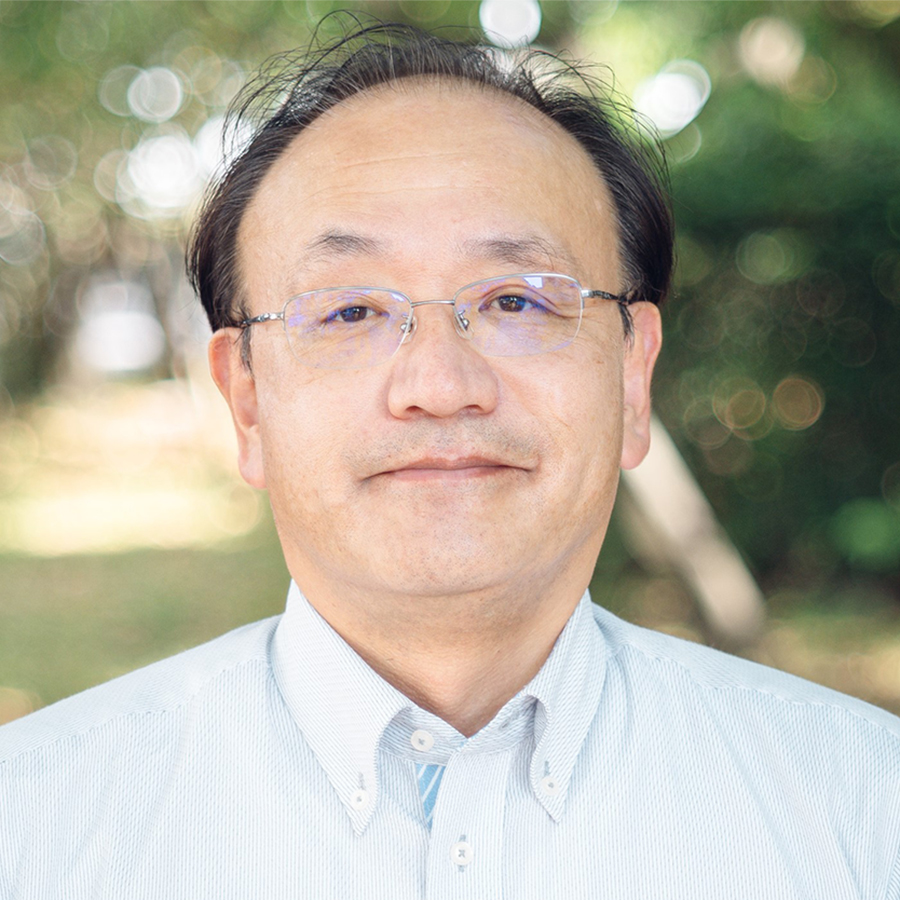
農学部長
寺岡行雄
あらた同窓会の会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より、同窓生の皆様から農学部学生及び教職員へのご支援を頂いておりますこと、厚くお礼申し上げます。この度、5年ぶりに「あらた同窓会名簿」が改訂・出版されると伺いご挨拶申し上げます。1908年の鹿児島高等農林学校設立以来、鹿児島大学農学部へと続く荒田のキャンパスで学ばれた、多くの皆様の足跡が同窓会名簿には刻まれており、この出版は大変喜ばしいものと思います。
さて、鹿児島大学は2004年(平成16年)に国立大学法人となり、2022年(令和4年)度からは第4期中期計画期間に入りました。減少し続けていた国からの運営費交付金が下げ止まりの傾向にありますが、就職率や科学研究費補助金の獲得などによる大学間での成績の比較により、予算額が増減額する仕組みが取り入れられてきました。教員数が減少する中、学生の教育研究の質を落とさないよう、努力をしているところです。組織的な取り組みとしては、ICT化等による先進的スマート農畜林水産業を創出する人材や食の安全・品質保証・グローバル化に適応可能な人材の養成等、農学分野と水産学分野双方の高度な知識を有する人材養成に対応するため、2019年(平成31年)4月に大学院農学研究科と大学院水産学研究科の両研究科を統合し、大学院農林水産学研究科を発足させました。
先の同窓会名簿が出されてからの5年間にあった最も大きな出来事は、新型コロナ感染症への対策としての教育研究環境の変化です。講義室や実験室、あるいは農場や演習林での授業が当たり前でしたが、2020年(令和2年)度からインターネットを利用したオンラインやオンデマンド授業が始まりました。研究室へ来るのも必要最小限度にとどめることが求められました。それ以来、教職員も不慣れなインターネットを通じた講義の実施に取り組み、学生諸君の努力の甲斐あって、ネットを通じた教育が成果を上げてまいりました。2021年(令和3年)度からは、徐々に出校して対面での授業の機会を増やしてまいりましたが、2022年(令和4年)度が終わる現在でもマスクを外すことができない状態です。学生たちの顔をしっかりと覚えることが難しくなっており、卒業してゆく学生と農学部あるいは先生方との関係が希薄になるのではないかと危惧しております。このような中、この同窓会名簿が、同窓生の皆様の繋がりの証として、より一層の連携を深める大切な役割を果たしてくれるものと期待しております。 末尾になりますが、同窓生の皆様のますますのご健勝とご多幸を、ならびにあらた同窓会のご発展を心より祈念申し上げます。